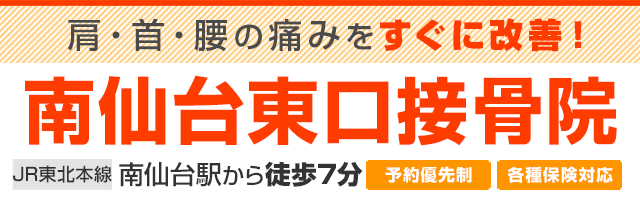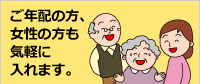巻き肩


こんなお悩みはありませんか?

首や肩のこりがひどくなっている
頭痛がよく起こる
疲れがなかなか取れない
呼吸が浅い
姿勢が悪くなっている
睡眠の質が低下している
腰痛など、背中に不快感がある
眼精疲労など、目の疲れが気になる
巻き肩について知っておくべきこと

巻き肩(まきかた)とは、肩が前方に巻き込まれた状態のことを指します。この状態は、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、運動不足などが原因で起こることが多いです。以下に、巻き肩について知っておきたいポイントをいくつかご紹介いたします。
巻き肩は、筋肉の不均衡や左右差、姿勢の悪さなどから生じます。特に、胸部の筋肉が緊張し、背中の筋肉が弱くなることが大きく影響します。
巻き肩の状態になると、肩こりや首の痛み、背中の不快感などが見られ、それらが悪化する可能性もあります。また、呼吸が浅くなることもあります。
巻き肩を放置すると、慢性的な痛みや不快感につながるおそれがあるため、早めに対処することが大切です。
症状の現れ方は?

巻き肩は、胸部の筋肉が硬くなり、肩が前方に出ることで引き起こされます。肩から胸部にかけての筋肉がこることで、筋肉が縮まり、その結果として姿勢不良だけでなく、いくつかの症状があらわれる場合があります。
主な症状として、大きく二つが挙げられます。
一つ目は、肩や首がこりやすくなることです。筋肉の柔軟性が失われると血行が悪くなり、筋肉のこりが長引くことで、頭痛やストレートネックにつながる可能性があります。
二つ目は、呼吸機能が低下しやすくなることです。巻き肩の状態により肋骨の可動域が制限され、換気量が低下するおそれがあります。呼吸機能だけでなく、自律神経系にも影響を及ぼすことがあります。
その他の原因は?

巻き肩の原因としては、大きく二つが挙げられます。
一つ目は、長時間のスマートフォン操作やデスクワークによるものです。これらの動作は、いわゆる猫背の姿勢になっていることが多く、画面をのぞき込む姿勢や肩に力が入った状態が続くことで、巻き肩が引き起こされる可能性があります。
二つ目は、睡眠時の姿勢が横向きになっていることです。理由としては、横向きで寝ていると上半身の体重が肩にかかり、肩が前に出てしまうためです。特に、寝ている間に寝返りが少ない方や、休日に横向きで長時間過ごされている方は、巻き肩になる可能性が高くなります。
巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩を放置すると起こる可能性がある影響
巻き肩をそのままにしておくと、以下のような影響が出る可能性があります。
1.肩こり・首こりの悪化
巻き肩になると肩が前方に出て、首や肩の筋肉が常に引っ張られた状態になります。その結果、血行が悪くなり、肩こりや首こりがひどくなることがあります。
2.頭痛やめまいが起こりやすくなる
首の筋肉がこわばることで、頭部への血流が悪くなり、緊張型の頭痛やめまいが生じる場合があります。
3.猫背や反り腰の悪化
巻き肩の影響で姿勢が崩れると、猫背や反り腰が進行しやすくなります。それにより、腰の不調や全身のバランスが乱れることがあります。
4.呼吸が浅くなる
胸郭(肋骨まわり)が圧迫されることで肺が十分に広がらず、呼吸が浅くなる可能性があります。呼吸が浅くなることで、疲れやすくなったり、集中力が続きにくくなったりすることがあります。
5.四十肩・五十肩のリスクが高まる
肩関節の動きが制限されると、将来的に四十肩や五十肩のリスクが高まる可能性があります。
6.見た目の印象に影響が出る
巻き肩によって前かがみの姿勢になると、実年齢よりも老けて見えたり、自信がなさそうな印象を与えてしまったりすることがあります。
巻き肩によるこれらの不調や影響を軽減していくためには、日常的にストレッチやエクササイズを取り入れることが大切です。
当院の施術方法について

当院で行っている巻き肩への施術について
当院では、巻き肩による不調の軽減が期待できるよう、以下のような施術を行っております。
1.姿勢分析・評価
まずは立ち姿勢や座り姿勢をチェックし、どの筋肉に緊張があるのか、どの部分に歪みが見られるのかを評価いたします。
2.筋肉のほぐし(手技療法)
巻き肩の方は、大胸筋・小胸筋・前鋸筋などが硬くなっていることが多いため、これらの筋肉を手技でほぐし、柔軟性を引き出していきます。
また、逆に菱形筋・僧帽筋・肩甲骨周囲の筋肉は弱くなっている傾向があるため、これらを活性化させる施術もあわせて行います。
3.背骨・肩甲骨の調整(骨格矯正)
巻き肩は肩だけでなく、背骨(特に胸椎)の可動性が低下していることも原因の一つです。
そのため、背骨や肩甲骨の可動域を広げるための矯正を行い、自然な位置へと整えていきます。
4.姿勢矯正ストレッチ・エクササイズ指導
施術だけでは一時的な効果にとどまることが多いため、胸部の筋肉を伸ばすストレッチや、肩甲骨を内側に寄せるトレーニングなどをご指導いたします。
特に、日常的に肩甲骨を引き寄せる意識を持つことで、良い姿勢を維持しやすくなります。
5.日常生活へのアドバイス
巻き肩の原因には生活習慣も大きく関係しています。そのため、以下のような点についてもアドバイスをさせていただきます。
デスクワーク中の姿勢
スマートフォンを見る際の注意点
就寝時の枕の高さや姿勢
患者様の生活スタイルに合わせて、無理なく実践できる内容をご提案いたします。
当院での施術とご自身でのセルフケアを併用することで、巻き肩による不調の軽減が期待できます。
軽減していく上でのポイント

巻き肩の軽減にはストレッチ・筋力トレーニング・姿勢の意識が大切です
巻き肩の軽減が期待される方法としては、まず胸部や肩まわりの筋肉をしっかりとほぐしたり、伸ばしたりするストレッチを行うことが効果的です。
また、ストレッチだけではなく、背中の筋力トレーニングを取り入れることも重要です。背中の筋肉を鍛えることで、肩甲骨を引き寄せる力が働き、背中の筋肉が強化されることで肩の内旋が整い、巻き肩の軽減が期待できます。
ここまでストレッチや背中のトレーニングについてご紹介してきましたが、最も大切なのは、根本的な見直し、つまり日常的に姿勢を意識することです。
どういうことかと申しますと、現代では長時間のデスクワークや運転が日常的になっており、身体が疲れると自然と背中が丸まってしまい、いわゆる猫背の姿勢を取りやすくなります。そのとき、肩も内側へ入りやすくなり、巻き肩を招きやすくなってしまうのです。
そうならないようにするためにも、座って作業をするときは胸を開き、肩を軽く後ろに引くように意識することが大切です。また、長時間座ったままにならないよう、作業の合間に適度に身体を動かすよう心がけましょう。
さらに、歩いているときにはスマートフォンを操作せず、前を向いて歩くことを意識することも、正しい姿勢を保つうえで非常に大切です。
監修

南仙台東口接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:福島県福島市
趣味・特技:料理、Netflix